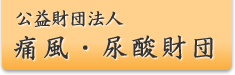痛風・尿酸ニュース
遺伝子組み換え技術を用いて、マウスからヒトへの進化の過程を模倣する
細山田 真(帝京大学薬学部 人体機能形態学)

はじめまして。私は実験動物(マウス:はつかねずみ)を用いたプリン(体)の研究を行っています。(化学としてはプリンと呼ぶのが正しいのですが、世間ではプリン体になじみがありますので、ここではこの表記をすることにします)。これまで何度も財団に研究を助成していただき、大変お世話になってきました。最近論文を公表した研究について、お話ししたいと思います。
プリン(体)に酸素原子が1つ付いたヒポキサンチンと呼ばれる物質から、酸素原子が3つ付いた尿酸を生成する酵素がキサンチン酸化酵素(キサンチンオキシダーゼ)と呼ばれるものです。痛風・高尿酸血症の方々は体内での尿酸の生成を減らすために、このキサンチンオキシダーゼの働きを抑える働きのあるフェブキソスタット(フェブリックなど)やトピロキソスタット(トピロリック、ウリアデック)などの薬を服用されている方もいらっしゃるかもしれません。遺伝子変異によりキサンチンオキシダーゼの機能が全く失われている方はキサンチン尿症という遺伝性疾患となるのですが、この疾患の方はたまに尿路結石が認められるものの、多くはこれといった症状もありません。ところが、同じように遺伝子を変異させてキサンチンオキシダーゼの機能を無くしたマウスは、生後8週の子供のうちに腎不全で亡くなってしまいます。このように、プリン(体)の研究ではマウスとヒトで得られる結果が異なること(種差と言います)が多く、糖やタンパク質(アミノ酸)など他の物質の研究がマウスとヒトで同じような結果が得られるのに比べて、プリン(体)の研究が難しい点です。
サルを除いて、マウスは哺乳類の中では最もヒトに近い動物なのですが、それでもこのような種差が生じるのは、マウスからヒトに進化する過程で体内でのプリン(体)の生成や分解において変化が起きたためです。そこでマウスでは機能していてヒトでは機能が失われた遺伝子(偽遺伝子と呼ばれます)のひとつである、腸管でヒポキサンチンを体内に取り込む働きをするSNBT1という分子の遺伝子を変異させて機能を無くすことにより、キサンチンオキシダーゼ欠損マウスの寿命が延びて、成人ならぬ成マウスにすることができました。それでもまだ、ヒトのキサンチン尿症患者と同様に天寿を全うするというわけではなく、腎障害も呈していました。ヒトに至る進化の過程ではさらに多くの偽遺伝子化がプリン(体)の代謝に関係する遺伝子において生じたのだろうと思います。
今後は、このような偽遺伝子化をマウスで進め、プリン(体)の代謝においてヒトのモデルとなるようなマウスを作出したいと考えています。偽遺伝子化は着手したら結果が出るまでに2年はかかるのですが、着実に研究を進めて行きたいと思います。
HOME » 痛風と尿酸について知りたい方へ » 痛風・尿酸ニュース » 遺伝子組み換え技術を用いて、マウスからヒトへの進化の過程を模倣する