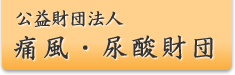痛風・尿酸ニュース
薬用植物園のすすめ
山岡 法子(帝京大学薬学部 臨床分析学研究室)

痛風・尿酸財団より本ページのご依頼をいただいたのは10月初旬でした。薬学部に所属し、漢方薬やその材料となる生薬について講義を担当している私は、生薬の基原となる薬用植物を育てて展示する「薬用植物園」の管理もしています。現代医薬品の多くが植物や菌類等に含まれる成分をもとにして開発されていることから、薬用植物園は薬学教育や研究になくてはならないものという位置づけの施設です。10月初めは、薬学部3年生の講義の1コマとして植物観察を行い、また薬剤師さんの認定講座として薬用植物園研修会も毎年の行事としてあるので、片道2時間、電車とバスを乗り継いで園に行き植物の解説をします。
さて、秋の薬用植物園の見どころといえば、その一つがイヌサフランと言ってもいいでしょう。ユリ科植物イヌサフランの花は、きれいなピンク色~うす紫色で、この時期の薬草園の中でひときわ華やかで目を引きます。花が美しいので園芸用に品種改良されたものは園芸店やホームセンターで“コルチカム”として売られています。痛風治療で使用される「コルヒチン」の原料となるこの植物をご覧になったことはありますか。春には地面から芽を出し葉が伸びるのですが、夏にはその葉が枯れてなくなります。この春の芽だしの時期の葉がちょうどギョウジャニンニクと形状がよく似ているため、毎年のように誤食による食中毒のニュースを見ます。9~10月になると、今度は花のつぼみだけが地面からニョキッと出てきます。なんとも綺麗で不思議な植物ですが、イヌサフランは痛風治療にとって重要な医薬品の基原となる植物です。
秋の薬用植物としては、ゲンノショウコも良く知られる薬草です。地面を這うように枝分かれして広がるフウロソウ科の植物で、「現の証拠」という名は下痢止めとして服用するとすぐに験(効果)が現れることからその名前が付けられたそうです。1センチほどの可愛らしい小さな五弁花は、西日本ではピンク色(赤花)、東日本では白色(白花)が一般的に見られます。本学の園は神奈川県相模原市にありますが、赤と白と両方の花が咲いています。
薬用植物園の管理をするようになって9年が経過しましたが、どんどんその魅力に引かれています。季節ごとに見頃の花は変わり、春のシャクヤク、ボタンなどは薬用種でも大変美しく、漢方薬に使用されるその薬の用途を知れるとなれば薬用植物観察は何とも楽しいものです。ほとんどの植物には説明の札が立てられているので、植物の知識がなくても老若男女誰でもが植物観察を楽しむことができます。また、あまり知られていないことですが、絶滅危惧種の保護にも一役買っています。まずは春と秋の開花が多い季節に、お近くの薬用植物園に季節の薬草を見に行きませんか。
HOME » 痛風と尿酸について知りたい方へ » 痛風・尿酸ニュース » 薬用植物園のすすめ